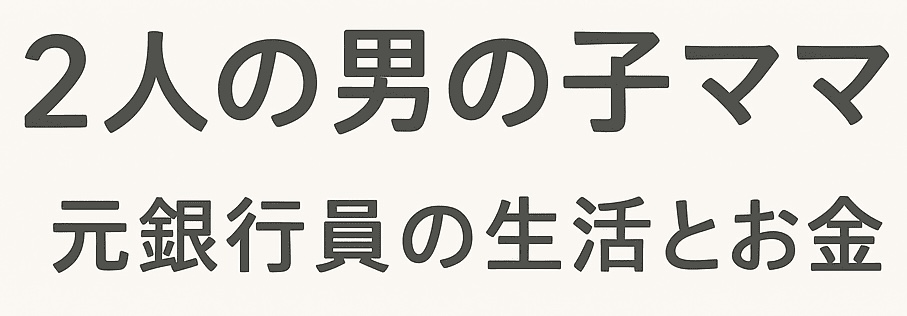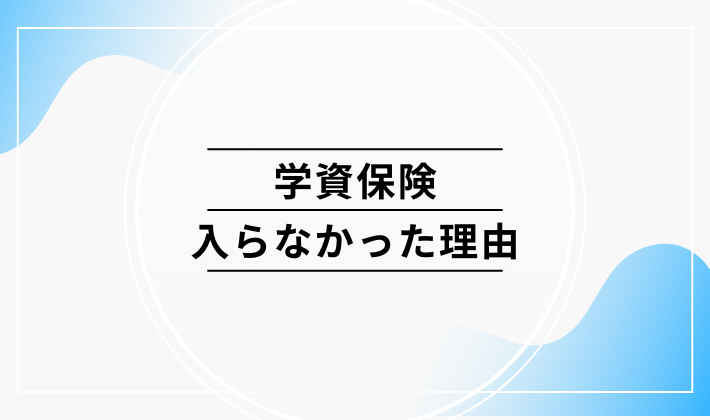はじめに
「みんな入ってるみたいだし、やっぱり学資保険って必要?」
子どもが生まれたとき、私もそう思いました。
でも、元銀行員としての経験と2児ママとしての感覚から、我が家は「入らない」という選択をしました。
この記事では、なぜ学資保険に入らなかったのか、代わりにどう教育費を準備しているかをお伝えします。
学資保険ってどんなもの?
学資保険は、子どもの教育資金を目的とした積立型の保険。保険料をコツコツ支払うことで、進学時期にお金を受け取れる仕組みです。
学資保険のメリット
- 強制的に積み立てられる
- 万が一の保障がある(親が亡くなった場合、保険料免除)
- 商品によっては返戻率100%超
学資保険のデメリット
- 途中解約で元本割れのリスク
- 使い道・引き出し時期が限定される
- 金利が低く、利回りはあまり良くない
我が家が入らなかった3つの理由
① 返戻率がそこまで高くない
銀行時代の感覚で見ると、「年利で考えると効率が良くないな」と感じました。
返戻率は多くても105%程度。たとえば月1万円×18年で216万円払い込み、受取は約226万円。正直、10〜18年かけて+10万円なら微妙だと感じました。
② 途中でお金を使いたくなるかも
育児は予測できない出費の連続。塾、留学、転居など予想外の出費に柔軟に対応したい。保険は「決まった時期にしか引き出せない」=使い勝手が悪いのがネックでした。
③ 他の方法の方が柔軟で効率的
元銀行員として「保険は万が一の備え、貯蓄は別で考えるべき」と思っています。なので、以下の方法で教育費を準備しています。
実際にやっている教育費の貯め方
① 児童手当は全額貯金
手をつけず、毎月専用口座へ自動振替。子ども1人あたり約200万円もらえるので、進学時にまとめて使う予定です。
② ジュニアNISA・NISAで少額投資
2人の子どもそれぞれのジュニアNISA口座をつくって、毎月投資をしていました。(ジュニアNISAは2023年末をもって廃止されたので現在は申し込むことができません)
現在は、楽天証券NISAをしていて、月5万円積立。リスクはありますが、長期運用ならプラスになる可能性が高いと判断。
児童手当で“守り”、NISAで“攻め”の資産形成をしています。
③ 家計管理で浮いた分を積立
マネーフォワードMEで家計を見える化。予算内でおさまった月は、余剰分を教育費口座へ入金。家計簿を使うと無駄が見えて、意外と貯まります。
学資保険が合う人/合わない人
| 合う人 | 合わない人 |
|---|---|
| 強制的に貯金したい人 | 自分で資産運用できる人 |
| 万が一の備えを重視する人 | 柔軟にお金を使いたい人 |
| 貯金が苦手な人 | リスクとリターンを考慮できる人 |
保険を比較・家計の見直しをするならプロに相談
我が家は入らなかったけど、比較して納得して選ぶことがいちばん大事。
保険の見直しを含めて家計の見直しをしてみてはいかかでしょうか?
まとめ
我が家は、学資保険に入らないという選択をしました。
それは「利回り」「柔軟性」「使いやすさ」を重視した結果です。
でも、家庭によって正解は違います。大事なのは、自分たちに合った方法を見つけて納得して決めること。この記事がそのヒントになればうれしいです。